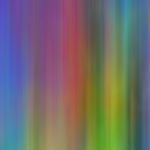異物混入ゼロを目指す!品質トラブル防止の現場改善術
iafpe
- 0
製薬業界で働く私たちにとって、「異物混入」という言葉は、単なる品質トラブルでは済まされない、非常に重い意味を持ちます。
患者様の健康と安全に直結するからこそ、そのリスクは絶対に避けなければなりません。
こんにちは。
製薬会社の品質保証部でマネージャーを務めております、佐藤 陽一と申します。
医薬品業界で18年、そのうち12年を品質管理の現場で過ごしてきました。
何を隠そう、私自身もかつては異物混入トラブルに頭を悩ませた一人です。
しかし、現場の仲間たちと試行錯誤を重ね、担当ラインで異物混入ゼロを3年間継続するという成果を出すことができました。
この経験から学んだのは、「品質はルールを守るだけで達成できるものではない」ということです。
品質は、現場一人ひとりの意識と行動によって「創り上げていくもの」なのです。
この記事は、今まさに異物混入のリスクに直面し、悩んでいるあなたのために書きました。
私が現場で培ってきた、今日から実践できる具体的な改善術を、余すところなくお伝えします。
この記事を読み終える頃には、あなたの現場でも異物混入ゼロへの確かな一歩を踏み出せるはずです。
目次
なぜ異物混入は起こるのか?原因を正しく捉える
異物混入を防ぐ第一歩は、敵の正体、つまり「なぜ起こるのか」を正確に理解することから始まります。
原因が分からなければ、正しい対策は打てません。
ここでは、異物混入の根本原因を深掘りしていきます。
よくある異物混入のタイプと発生源
まず、私たちの製造現場で遭遇する可能性のある「異物」には、どのようなものがあるでしょうか。
代表的なものをリストアップしてみましょう。
- 人体由来: 毛髪、体毛、皮膚片など。作業者から発生する最も基本的な異物です。
- 衣服由来: 作業着から出る繊維くず、糸くずなど。
- 環境由来: 虫、カビ、ホコリなど。製造環境の清浄度が直接影響します。
- 設備由来: 装置の摩耗による金属片、パッキンの劣化によるゴム片、潤滑油など。
- 資材由来: 原材料に含まれる不純物、包装材の破片など。
これらの異物は、製造工程のあらゆる場所で発生・混入する可能性があります。
現場で見逃されがちな「隠れリスク」
上記の代表的な異物以外にも、現場には見過ごされがちな「隠れリスク」が潜んでいます。
例えば、こんな経験はありませんか?
「洗浄後の器具に、目には見えない微細な残留物が付着していた」
「手順書にない『良かれと思って』の行動が、新たな汚染源を生んでしまった」
「設備のわずかな隙間が、虫の侵入経路になっていた」
こうした隠れリスクは、日常業務の「慣れ」や「思い込み」の中に隠れています。
「いつもこうだから大丈夫」という思考が、最も危険なリスクとなり得るのです。
ヒューマンエラーの構造とGMP視点での分析
異物混入の根本原因を突き詰めると、その多くが「ヒューマンエラー」に行き着きます。
しかし、単純に「担当者のミス」で片付けてはいけません。
GMP(Good Manufacturing Practice)の視点では、エラーは個人だけでなく、仕組みの問題として捉えます。
- なぜ、その人はエラーを犯したのか?
- 手順書が分かりにくかったのではないか?
- 作業環境がエラーを誘発しやすかったのではないか?(例:暗い、狭い)
- 教育・訓練が不十分だったのではないか?
- 疲労や焦りを生むような作業計画ではなかったか?
重要なのは、個人を責めるのではなく、エラーが起きにくい環境と仕組みを構築することです。
これが、GMPにおけるヒューマンエラー対策の基本的な考え方です。
異物混入を「ゼロ」にする難しさと現実的目標の設定
「異物混入ゼロ」は、私たちが目指すべき究極の目標です。
しかし、その達成が非常に困難であることも事実です。
だからこそ、私たちは現実的な目標設定から始めるべきです。
まずは、自部署の現状を正確に把握し、「前月比でクレームを1件減らす」「特定の異物(例:毛髪)の混入を撲滅する」といった、具体的で測定可能な目標を立てることが大切です。
小さな成功体験を積み重ねることが、やがて大きな目標である「ゼロ」へと繋がっていきます。
事例で学ぶ!現場で起きた異物混入とその対応
理論だけでは、品質管理のリアルは語れません。
ここでは、私自身の苦い経験をお話しさせてください。
これは、私が入社3年目に経験し、品質への価値観を根底から変えることになった、忘れられない出来事です。
ライターが経験した実際の混入事案(入社3年目の事例)
それは、ある注射剤のロットで起きました。
最終検査工程で、製品バイアル内に微細な「黒い浮遊物」が発見されたのです。
若かった私は、頭が真っ白になりました。
「まさか自分の担当ラインで…」という衝撃と焦りだけが心を支配していました。
その日の夜から、私たちは原因究明のためにラボに泊まり込みました。
発見された異物はあまりに小さく、特定は困難を極めました。
原因究明のプロセスとチーム対応のリアル
私たちは、考えられる全ての可能性を一つずつ潰していくしかありませんでした。
- 異物の特定: まず、分析チームが顕微鏡と分析装置を駆使して異物の正体を突き止めました。結果は「ステンレス鋼の微粒子」。製造設備の一部である可能性が濃厚になりました。
- 発生源の調査: 次に、製造チームとエンジニアリングチームが、製造ラインの全設備を分解し、部品の一つひとつをチェックしました。数時間にわたる調査の末、ある撹拌機の軸受け部分に微細な摩耗痕を発見したのです。
- なぜなぜ分析: なぜ摩耗は起きたのか?私たちは「なぜ」を5回繰り返しました。「軸受けが摩耗した」→「なぜ?」→「潤滑が不十分だった」→「なぜ?」→「定期メンテナンスのチェックリストに潤滑油の確認項目がなかった」…。根本原因は、手順書の不備にありました。
このプロセスは、決して一人ではできませんでした。
分析、製造、エンジニアリング、そして品質保証。
部署の垣根を越えたチーム一丸の対応があったからこそ、根本原因に辿り着けたのです。
監査対応と外部への説明責任のポイント
原因究明と並行して、私たちは規制当局への報告と監査の準備を進めました。
この時、上司から叩き込まれたのは「事実を隠さず、客観的データに基づいて誠実に説明する」という姿勢でした。
- 事実関係の時系列での整理
- 原因究明プロセスの詳細な記録
- 暫定措置と恒久対策の明確な提示
- 健康被害リスクの科学的評価
これらの資料を準備し、監査では真摯に対応しました。
厳しい指摘も受けましたが、私たちの誠実な対応が、最終的には信頼の回復に繋がったと信じています。
この経験がもたらした品質への価値観の変化
この一件は、私に品質管理の厳しさと、その本質を教えてくれました。
品質とは、ただ規格に適合しているかを確認するだけの作業ではありません。
それは、起こりうる全てのリスクを予測し、先手を打って潰していく創造的な活動なのだと。
そして何より、品質は一人のスーパースターではなく、現場全員のチームワークによって支えられているということを、身をもって学びました。
この経験こそが、私の品質保証という仕事の原点となっています。
異物混入ゼロを目指す現場改善のステップ
では、具体的にどうすれば異物混入を防ぐことができるのでしょうか。
ここでは、私が現場で実践してきた改善活動を、5つのステップに分けてご紹介します。
これは、どんな現場でも応用可能な、普遍的なプロセスです。
ステップ①:発生源マップの作成とリスクの見える化
まず最初に行うべきは、自分たちの製造工程に潜むリスクを「見える化」することです。
- 工程の分解: 製造工程を、原材料の受け入れから最終製品の箱詰めまで、できるだけ細かく分解します。
- リスクの洗い出し: 各工程で「どんな異物が」「どこから」「どのように」混入する可能性があるかを、チーム全員でブレインストーミングします。
- マップへの落とし込み: 製造ラインの図面に、洗い出したリスクを付箋などで貼り付け、「異物発生源マップ」を作成します。
このマップを作ることで、チーム全員が「どこに危険が潜んでいるか」を共通認識として持つことができます。
ステップ②:GMPに基づく作業手順の最適化
リスクが見えたら、次はそのリスクを潰すためのルール、つまり作業手順書(SOP)を最適化します。
- 具体性の追求: 「清掃を徹底する」といった曖昧な表現ではなく、「どの洗剤を使い、どのブラシで、どの方向に、何回擦るか」まで具体的に記述します。
- 写真や図の活用: 文章だけでは伝わりにくい作業は、写真やイラストを多用し、誰が見ても同じ作業ができるように工夫します。
- 根拠の明記: なぜその作業が必要なのか、その根拠(例:「○○の汚染を防ぐため」)を明記することで、作業者の理解を深め、遵守率を高めます。
ステップ③:人的エラーを防ぐ教育と行動観察
完璧な手順書があっても、実行するのは「人」です。
ヒューマンエラーを防ぐためには、継続的な教育が欠かせません。
- 座学と実践の組み合わせ: 手順書を読むだけの座学だけでなく、実際に作業をしながら教えるOJT(On-the-Job Training)を重視します。
- 定期的な行動観察: マネージャーやリーダーが定期的に現場を巡回し、作業者が手順通りに作業しているかを確認します。この時、決して監視や粗探しではなく、対話を通じて改善点を見つけるという姿勢が重要です。
- 力量評価: 作業者一人ひとりのスキルを客観的に評価し、苦手な作業については追加のトレーニングを行うなど、個別のフォローアップを実施します。
ステップ④:現場主導の改善文化づくり
改善活動は、経営層や管理者から押し付けられるものであってはなりません。
最も効果的なのは、現場の作業者自身が主役となって改善を進める文化を育むことです。
「ここの作業、もっとこうしたらやり易いんじゃない?」
「この器具、汚れが溜まりやすいから形状を変えられないかな?」
こうした現場からの「ヒヤリハット」や改善提案を積極的に吸い上げ、良い提案はすぐに実行し、表彰する仕組みを作りましょう。
自分たちの声で職場が良くなっていく実感は、作業者のモチベーションを飛躍的に高めます。
ステップ⑤:継続的なCAPAとモニタリング体制の構築
一度改善して終わり、では意味がありません。
その改善策が本当に効果を上げているかを確認し、さらなる改善に繋げる仕組みが必要です。
それがCAPA(是正措置・予防措置)の考え方です。
- モニタリング: 異物混入の発生件数やクレーム件数などのデータを継続的に収集・監視します。
- 逸脱の調査: 目標値を逸脱した場合、その根本原因を徹底的に調査します(なぜなぜ分析など)。
- 是正・予防措置: 根本原因を取り除くための是正措置と、再発防止・水平展開のための予防措置を計画・実行します。
- 有効性の評価: 実施した措置が有効であったかを、モニタリングデータに基づいて評価します。
このCAPAサイクルを回し続けることが、品質レベルを継続的に向上させるためのエンジンとなります。
今すぐ使える!品質トラブル防止の現場チェックリスト
ここまでのステップを踏まえ、あなたの現場ですぐに使えるチェックリストを作成しました。
チームメンバーと一緒に、自分たちの職場がどのレベルにあるかを確認してみてください。
一つでも「No」があれば、そこがあなたの改善のスタート地点です。
チェックポイント①:作業環境と清掃の徹底
- [ ] 床や壁、設備にひび割れや塗装の剥がれはないか?
- [ ] 排水溝は清掃され、悪臭や害虫の発生源になっていないか?
- [ ] 清掃に使用する道具は、用途別に色分けされ、適切に保管されているか?
- [ ] 「清掃記録」は毎日正確に記入され、責任者によって確認されているか?
チェックポイント②:異物の早期発見体制の有無
- [ ] 原材料の受け入れ時に、外観検査やサンプリング検査を実施しているか?
- [ ] 製造ラインの適切な箇所に、フィルターや金属検出機が設置・管理されているか?
- [ ] 目視検査を行う場所は、十分な明るさが確保されているか?
- [ ] 検査員の視力や集中力に関する定期的なケアは行われているか?
チェックポイント③:作業手順書の整備と遵守状況
- [ ] 全ての重要な作業について、写真や図入りの分かりやすい手順書があるか?
- [ ] 手順書は、現場の作業者がいつでもすぐに参照できる場所に保管されているか?
- [ ] 手順書の内容は、少なくとも年1回は見直され、最新の状態に更新されているか?
- [ ] 手順書からの逸脱があった場合、その記録と原因調査が確実に行われているか?
チェックポイント④:教育記録と力量評価の活用
- [ ] 新人作業員に対する教育プログラムは標準化されているか?
- [ ] 全ての作業員の教育訓練記録は、抜け漏れなく保管されているか?
- [ ] 作業者のスキル(力量)を定期的に評価し、再教育が必要な人を特定する仕組みがあるか?
- [ ] 力量が不十分な作業者を、一人で重要な工程に就かせていないか?
チェックポイント⑤:日常点検と改善提案の仕組み
- [ ] 始業前点検リストがあり、毎日確実に実施・記録されているか?
- [ ] 現場の作業者が「ヒヤリハット」や改善提案を気軽に報告できる仕組み(提案箱など)があるか?
- [ ] 提出された提案に対して、迅速なフィードバックと対応が行われているか?
- [ ] 優れた改善提案を行ったチームや個人を、表彰する制度があるか?
未来を見据えて:異物混入ゼロのための組織的アプローチ
現場レベルの改善と同時に、会社全体として品質文化を醸成していく視点も不可欠です。
ここでは、より長期的で組織的なアプローチについて考えてみましょう。
グローバル基準(FDA/MHLW)に沿った品質保証体制
私たちの作る医薬品は、国内だけでなく世界中の患者様に使用される可能性があります。
そのためには、FDA(米国食品医薬品局)やMHLW(厚生労働省)といった国内外の規制当局が求めるグローバル基準の品質保証体制を構築する必要があります。
これは、単に査察をクリアするためだけではありません。
世界トップレベルの基準に自らを合わせることで、組織全体の品質意識と管理レベルを底上げすることができるのです。
特にCAPAシステムの適切な運用は、FDA査察でも最重要視される項目の一つです。
品質文化を浸透させる社内施策とその継続性
品質文化は、一朝一夕には築けません。
継続的な働きかけが必要です。
- 経営層からのメッセージ: 経営トップが、品質の重要性について繰り返し、自身の言葉で語りかける。
- 品質月間の設定: 年に一度、品質に関するポスター掲示や標語の募集、講演会などを集中的に実施する。
- 成功事例の共有: 異物混入防止に成功した部署の取り組みを、社内報や朝礼で全社に共有し、称賛する。
こうした地道な活動の積み重ねが、社員一人ひとりの心に「品質第一」の文化を根付かせます。
テクノロジー活用(AI・画像解析など)の可能性
近年、テクノロジーの進化が私たちの品質管理を大きく変えようとしています。
特に注目されているのが、AI(人工知能)を活用した画像解析技術です。
これまで熟練検査員の目に頼っていた微細な異物の検出を、AIが高精度で自動的に行ってくれる。
ある事例では、AIの導入で不良品の検知率が5倍に向上したという報告もあります。
もちろん、テクノロジーは万能ではありません。
しかし、人間が本来集中すべき「考える」「改善する」といった業務に時間を割くためにも、こうした先進技術を積極的に活用していく視点が、これからの品質管理には求められます。
そして、こうした検査技術と並行して、異物の原因究明や製品の品質保証に不可欠なのが、信頼性の高い分析機器の存在です。
例えば、旧:日本バリデーションテクノロジーズ株式会社のように、高精度な医薬品分析機器で業界を支える企業の技術も、私たちの品質保証体制をより強固なものにしてくれます。
「品質カフェ」など対話の場がもたらす効果
最後に、私が職場で実践して非常に効果があった取り組みを一つ紹介します。
それは、週に一度、部署のメンバーでお茶を飲みながら品質について気軽に語り合う「品質カフェ」です。
ここでは、上下関係なく、最近起きたヒヤリハット事例や、他社の品質トラブルニュース、改善のアイデアなどを自由に話し合います。
こうした公式の会議ではない、リラックスした対話の場が、実はチームの心理的安全性を高め、本音のコミュニケーションを促進するのです。
風通しの良い職場風土こそが、問題の早期発見と迅速な解決に繋がる最高の土壌だと、私は確信しています。
まとめ
長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。
最後に、この記事の要点を振り返りたいと思います。
- 異物混入防止の鍵は「見える化」と「行動変容」:まずはリスクを全員で認識し、それに基づき一人ひとりの行動を変えていくことが全ての基本です。
- 現場と組織が一体となった改善が不可欠:現場のボトムアップ改善と、経営層主導のトップダウンでの文化醸成、この両輪が揃って初めて品質は向上します。
- 今日から一歩を踏み出すために:小さな改善から始めよう:完璧を目指す必要はありません。まずはチェックリストの一つからでも、改善を始めてみてください。その小さな一歩が、未来の大きな成果に繋がります。
私が品質管理の仕事をする上で、バイブルのように大切にしている言葉があります。
それは、大学時代に出会った『品質は愛』という書籍のタイトルです。
製品の先にいる患者様を想う「愛」。
共に働く仲間を想う「愛」。
この気持ちがあれば、私たちの仕事は単なる作業ではなくなります。
あなたの現場でも、「品質は愛」を実感できる日が来ることを、心から願っています。
最終更新日 2025年7月8日 by iafpe