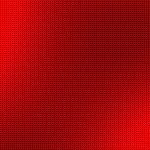企業出版の基本とメリットとは
iafpe
- 0
・企業出版を考えている
・企業出版のメリットや費用を知りたい
・企業出版の強みって何?
企業出版とは企業について広く知ってもらう為に、いわゆるブランディングを目的とした出版を指します。
といっても企業が自ら執筆するわけではなく、費用を負担する代わりにプロのライターなどに書いてもらう形となります。
ちなみに費用には出版に必要な紙や印刷、製本代も含まれるので、それなりのコストが掛かります。
個人だと1冊あたりが高額になる出版は難しいですが、予算を捻出できる企業であれば、個人よりもハードルが低いと思われます。
個人の自費出版は、複数人で費用を出して出版することもありますが、企業出版も同様に、複数社が費用を負担する形で本を出すことがあります。
自費出版と比べても更にハードルが下がる
出す本は基本的に1冊ですが、費用は複数で少しずつ負担することになるので、自費出版と比べても更にハードルが下がります。
余談ですが、企業が1社で本を出しているか複数で出しているかは、書籍に掲載される社名の数を確認すればだいたい分かります。
こういった出版のやり方はグループ企業だったり、医療法人に見られる傾向です。
言うまでもありませんが、会社のことを書いてもらう為の本なので、これまでの歩みを分かりやすくまとめたり、収益などに繋がるように魅力的に書かれるのが基本です。
つまり社史が写真を交えて掲載されたり、他社が取引したくなるような情報や、求人に結びつく内容なども盛り込まれます。
出版ではありますが、取引相手に名刺感覚で配る目的にも使われますから、1冊で会社の全体像が分かるようにまとめられます。
勿論、ネガティブなことは極力避けられますし、掲載するにしてもフォローをしっかりと入れるものです。
企業出版は時に企業イメージを左右することにもなりますから、ステークホルダーの方を向いて意識しつつ、株主の利益を損ねないように配慮して書かれます。
最低でも100万円くらいは覚悟する必要がある
企業向けに出版のサポートを行っている会社は、顧客が企業なので、相応の費用で請け負っています。
最低でも100万円くらいは覚悟する必要がありますが、それなりの費用が掛かる分、出版社は出版の魅力を積極的に伝えて出版にこぎ着けます。
企業の方から出版希望の持ち込みがあった場合も、希望に応える形で全面的なサポートが行われます。
いずれにしても問題は何冊作るか、どのように流通させるかで、書店に並べてもらうとなると途端にハードルが上がります。
当然ですが、書店が取り扱うとなれば最低部数のラインは上がりますし、売れる見込みがなければそもそも置いてもらえないです。
しかし起業家や会社経営者にとって魅力的な内容だと認められたり、一般にも売れる可能性があると判断されれば、書店も積極的に取り扱ってくれるでしょう。
結局のところ、流通が商業ルートに乗るかどうかは、売れる見込みがあって収益が期待できるか否かによります。
出版する企業が収益を目的としていなければ、書店に置いて本を手に取ってもらうのを望むのは難しいです。
逆にいえば、書店では手に入らない本として希少性を活かせますし、特別な相手に経営者のサイン入りで配布を行えば、話題が話題を呼んで注目を集める可能性もあります。
活用次第ではマーケティングに活かせる
戦略次第で欲しがる人が現れるのも、企業出版の可能性の1つだといえますし、魅力であってメリットにもなります。
自己満足に終始するのも良いですが、活用次第ではマーケティングに活かしたり、経営者の影響力を高めることにも繋がります。
ブランディングのツールや武器としても使えますし、ターゲットに企業を知ってもらう情報を伝えたり、集客や啓発に認知向上にも活用可能です。
企業出版は目的によって価値が上がったり下がったりもしますから、ただ本を書いて出すのではなく、どう活かすかも含めて検討することが大事です。
活用が上手くいけば費用の元はすぐに取れますし、売り上げが増えて収益がアップするのも夢ではなくなります。
経営課題を抱えているならそれを解決するツールとして、あるいはコストを抑えた宣伝にも活かせます。
企業出版の強み
肝心なのは企業出版には強みがあること、その点を理解してどう使うかを決めることです。
コスト面で考えると、Webサイトの方が長い目で見るとお得に思われますが、ランニングコストが掛からないのは出版の方です。
コスト重視ならSNSでしょうが、発信できる情報量が限られてしまったり、炎上などのネガティブな影響のリスクがあるのは考慮すべきポイントです。
Webサイト、もしくはブログの入口に使うのが無難なので、結局はこれらとの組み合わせが前提になります。
本は情報をまとめて形にするまでが大変ですが、完成すれば後は印刷と製本をするだけです。
ランニングコストは殆ど掛かりませんし、何年経っても腐ることはありませんから、気長に名刺代わりに少しずつ配ることもできます。
まとめ
内容が頻繁に変わる情報を盛り込むのには向きませんが、変わることのない社史を始めとした情報であれば、5年後も10年後も正確なままです。
そういう、興味を持ってもらう切っ掛けの1つとして、会社が費用を出して出版することには活用の幅やメリットがあるといえます。
最終更新日 2025年7月8日 by iafpe