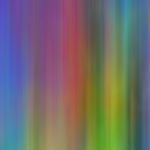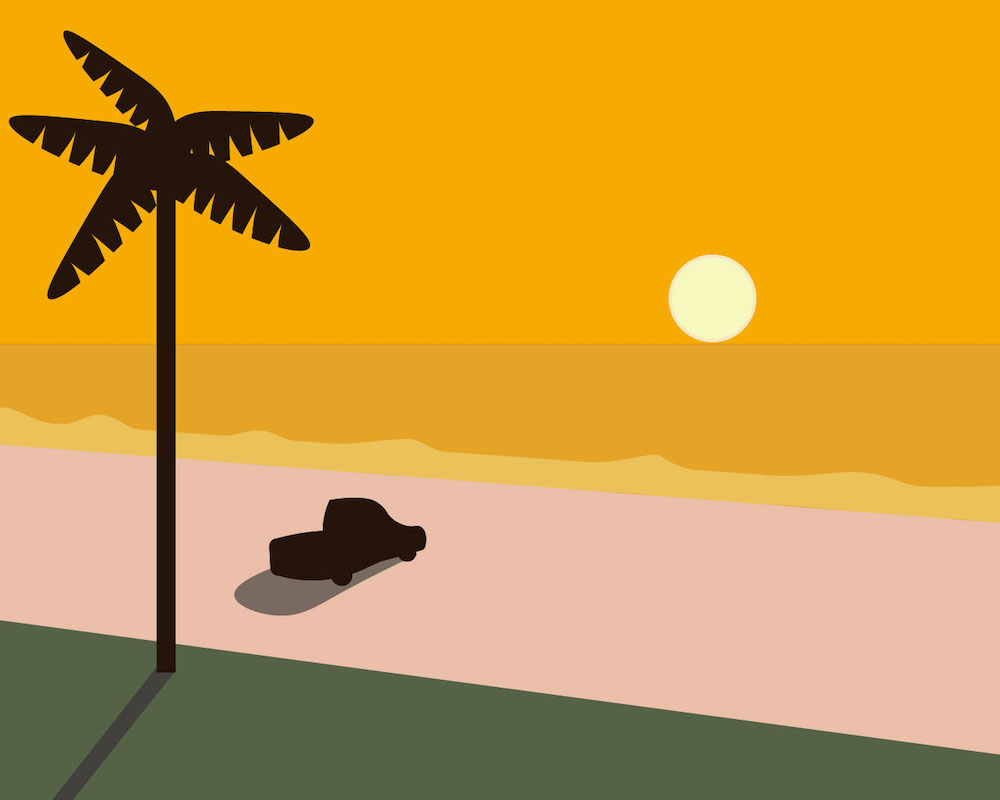障害年金の請求に関しては社労士に相談しよう
iafpe
- 0
1.障害年金の種類
障害年金にくくられるものには、障害基礎年金や障害厚生年金などの社会保険が由来のものと障害補償年金のような労働法及び労災が由来のものがあります。
障害補償年金は、労働基準法で使用者に支払うことが要請される障害補償を労災の仕組みで国が肩代わりする仕組みの年金であり、一般的な障害年金とは言えないです。
そのため、ここでは障害年金は社会保険由来の障害基礎年金と障害厚生年金のことを指すことにします。
障害基礎年金と障害厚生年金は、2階建ての年金制度にあるように併給されることが多いです。
また、障害基礎年金と老齢厚生年金という組み合わせや障害基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせも、レアな事例ですが可能です。
一方で、障害基礎年金とその他の基礎年金(老齢年金や遺族年金)を併給することはできず、また老齢基礎年金に付加される付加年金も障害基礎年金と併給されません。
2.障害年金はどのようなケースで受け取ることができるのか?
では、障害年金はどのようなケースに受け取ることができるでしょうか。
まず説明するのは障害基礎年金ですが、障害基礎年金は障害等級が1級と2級のものに支給され、1級の対象者には2級の対象者の4分の5倍の年金が支給されます。
障害基礎年金の受給者になった人は、3級に該当する場合には障害基礎年金は支給停止になりますが、支給停止は受給権が無くなるのではない点に注意が必要です。
障害厚生年金は、1級から3級まで支給され、1級は2級の4分の5倍、3級は2級の4分の3倍支給されるのが原則になります。
あくまでも2級に支払われる金額が基準になりますが、その金額の計算においては厚生年金の被保険者期間が300ヶ月に満たない被保険者が受給者になった場合であっても、300ヶ月加入していたものとして支給額が計算されます。
また、障害基礎年金の受給者が障害厚生年金の受給者になることは多いですが、3級である場合を除いて障害厚生年金のみが支給されることはないです。
なぜなら、障害基礎年金の受給権を得ることが障害厚生年金の支給判断のベースとなっているためで、また障害基礎年金の支給が認定される人は障害厚生年金の支給が認定されるのが通常だからです。
3.医師と社労士との連携が重要
障害年金の受給権を得るために重要になるのが、医師と社労士との連携です。
特に、医師は診断書を書くときに請求者に不利にならない書き方をすることが重要であり、それらの基準は社労士の方が良く把握しているため両者の連携が必要だといえます。
※参考ページ
障害年金申請を社労士に代行してもらう際の費用
請求者に不利にならない書き方とは、身体障碍者の場合は障碍の程度を正しく書けばよいのですが、精神障碍者や知的障碍者の場合には、請求者の障碍の見通しとして「予後不良」などの文言を書く必要があります。
精神障碍者などは見た目では障碍の程度が分からないことが多く、医師の診断書が障碍の状態を可視化するものとして唯一のものだと言えるからだといえます。
もちろん、請求者が記述することが必要とされる用紙も存在しますが、その用紙には請求者の主観が含まれているため、客観的な判断基準として診断書が重要なデータになります。
そのように大事な位置づけになっている診断書ですが、長年障害年金の請求に特化して携わっている社労士であれば、どのような診断書であれば請求が審査を通るかを熟知しているといえます。
そのため、それらの年金を請求したいと思っている人はそのような分野に特化した社労士を選ぶ必要があり、医師を選ぶこと以上に重要なことだと考えると良いでしょう。
4.遡及請求という制度について
そのほか、障害基礎年金と障害厚生年金に関して知っておくべき情報をいくつか紹介します。
まず、障害基礎年金にも障害厚生年金にも遡及請求という制度があり、それらの公的年金が時効として扱われる過去5年以内に遡って受給権を満たしていた期間の年金を請求できます。
それが意味するものは、最大5年分の年金が受給される可能性があるということで、障害基礎年金の2級のみの受給者であっても390万円前後の年金を受給できるということです。
もちろん、障害厚生年金も受給できる受給者や、障害等級が1級の受給者であればそれ以上の金額が受給できます。
しかしながら、遡及請求ができるのは通常の受給要件を満たす受給権者などに限られ、20歳前の傷病に基づく障害によって受給権を得られた受給者や事後重症と呼ばれる65歳までに以前の障害が悪化して受給権が得られたケースなどは遡及請求の要件からは省かれます。
ただ、事後重症の一種である基準障害による障害基礎年金や障害厚生年金の受給権者は、一般の受給権者と同等の扱いを受けます。
とにかく、障碍に基づく給付を年金という形で受け取ることができれば、障碍者やその家族の生活設計が立ちやすいことは事実です。
そのため、真剣に障碍に基づく給付(厚生年金保険法上4級以下で一時金をもらえることもあります)を受給することを考えている人は、社会保険に基づく年金制度に詳しい社労士に相談することをお勧めします。
最終更新日 2025年7月8日 by iafpe